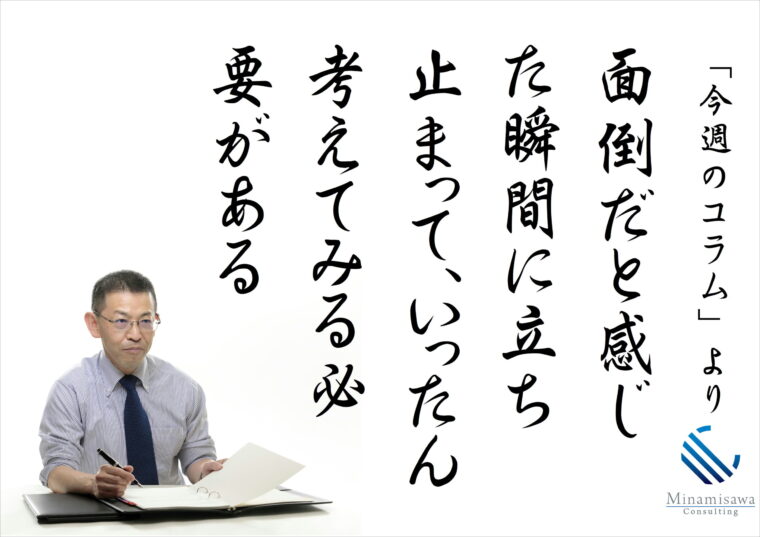
「南澤さん、毎回同じ作業をしているはずなのに、なぜか時間がかかってしまうんです…」―――これは、ある管理職の方から聞いた一言でした。
話を聞いていくと、決してサボっているわけでも、能力が極端に低いわけでもありません。むしろ、言われたことはきちんとこなす、真面目なタイプの方でした。それでも、「なぜか面倒」「やたら時間が取られる」という感覚だけが残っている。
南澤は、この“違和感”こそが非常に重要だと考えています。
単純に作業効率が悪い場合もありますし、忙しさの中で集中力が落ちていることもあるでしょう。ただ、それだけで片づけてしまうと、本質を見逃してしまいます。
「何か面倒だな」と感じた瞬間は、一度立ち止まって考えるサインなのです。
たとえば、Excelを使った集計作業。
毎月同じような報告資料を作成しているのに、毎回ゼロから表を作り、数字を貼り付け、体裁を整えている。本人は「仕事だから仕方ない」と思っていても、内心では「正直、面倒だな」と感じている。こうしたケースは決して珍しくありません。
Excelは、実は常に進化しています。世界中で同じように「面倒だ」と感じている人がいるからこそ、新しい機能や関数が生まれてきました。VLOOKUPやHLOOKUPの使い分けに悩む声から、XLOOKUPが登場したのもその一例です。
つまり、「面倒だ」と感じていた作業は、自分の能力が足りないのではなく、「やり方が古かっただけ」というケースが非常に多いのです。
管理職の立場になると、この視点はさらに重要になります。
部下が「時間がかかります」「忙しくて手が回りません」と言っていると、つい「要領の問題」「段取りの問題」と捉えてしまいがちです。しかし、その背景には「非効率なやり方を、疑わずに続けている」という構造が潜んでいることも少なくありません。
日々、何の疑いもなく仕事をしていると、知らず知らずのうちに時代に合わないやり方を続けてしまいます。特にITや業務ツールに関わる分野では、その差が少しずつ、しかし確実に積み重なっていきます。
メールの処理、報告書やPowerPointの資料作成など、「昔からこうやっているから」という理由だけで、管理職自身が古いやり方を踏襲しているケースも見受けられます。結果として、そのやり方が部下にも引き継がれ、組織全体の生産性を下げてしまうのです。
南澤自身も、最初からパソコンが得意だったわけではありません。正直に言えば、WordやExcelがほとんど使えない時代もありました。それでも、基本的な使い方を知っただけで、仕事のスピードは大きく変わりました。
たとえば、メール作成ひとつでも、ショートカットキーを知っているかどうかで作業効率は大きく変わります。Ctrl+Zが使えるかどうかだけでも、修正時のストレスはまったく違います。これは頭の良し悪しではなく、単に「知っているか、知らないか」だけの話です。
最近話題になるAIの活用も、本質的には同じです。
新しいツールを「難しそう」「よく分からない」と敬遠するか、「面倒だと感じる作業を減らせるかもしれない」と捉えるかで、その後の差は大きく広がっていきます。
もちろん、すべての社員が自発的に新しい情報をキャッチアップできるわけではありません。だからこそ、個人任せにしない視点が重要になります。
個人の努力に期待するのではなく、仕組みで解決する。
これは、現場レベルの話ではなく、経営の話です。
面倒なことを、愚直に一生懸命続ける社員は、とても貴重です。その姿勢自体は、間違いなく評価されるべきものです。一方で、「なぜ面倒なのか」「本当にそのやり方でいいのか」が放置されたままでは、現場は少しずつ疲弊し、やがて停滞していきます。
仕事は、疑い、改善し、進化させていくものです。
環境が変わり続ける中で、やり方だけが変わらないというのは、むしろ不自然とも言えるでしょう。
あらためて考えてみてください。
現場で感じられている「面倒だな」という感覚は、個人の甘えでしょうか。それとも、組織の仕組みや設計を見直すためのサインでしょうか。
もし、現場のあちこちで同じような“面倒”が発生しているとしたら、それは誰か一人の問題ではありません。経営としての点検機能が、少し弱ってきている可能性を示しているのです。
「面倒だな」と感じた瞬間は、成長の入り口です。その感覚が現場で埋もれてしまうのか、改善のきっかけとして拾い上げられるのか。そこにこそ、経営者の意思と、組織の未来が静かに表れていくのではないでしょうか。
著:南澤博史
◆音声でお楽しみいただけるポッドキャストのご案内
▶ ポッドキャストはこちらから(※Spotifyアプリが必要になります)
→ https://open.spotify.com/episode/3bE7d7Z0a4dimo4CJL6mhN?si=wEdXb5OPR5itljmwCJ7ujA
